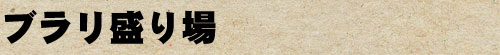
上方藤四郎が大阪新聞に掲載したコラム。
|
|
「織田作カレー」
(昭和39年9月29日 大阪新聞「ブラリ盛り場」掲載) |
千日前のもっとも千日前的体臭の濃厚な地点は、千日デパート南横の界わいであろうか。寄席・千日劇場のキップ売り場のあるところだ。むかい側に国際シネマ、国際日活がならんでいるが、いずれも戦後に新しくできた映画館である。ここもゴタゴタと飲食店が多いが、織田作之助が小説のなかに書いた自由軒という洋食屋のあるのもこの通りである。
自由軒は、大正時代、楽天地ハナヤカなりしころからの古いシニセで、大阪の大衆洋食の草分けみたいな店である。その時分は洋食のことを西洋料理といった。カレーライスが名物で、白い無地のでっかい洋ザラに、ややコワイ目のめしをいっぱい盛り、口中がカッカッする黄味がかったカレーをタップリかけ、そのうえに地タマゴを一つ、ぽんと落としてあった。タマゴの黄身の容積も、どこの店のものよりはるかに大きく、めしのそばにきざみしょうがを惜しげなくふんだんに添えてあった。ひとサラで満腹、独特の味だった。
いま、店の入り口に、「織田作好み・セイロン風・ドライカレー」という立て看板がでている。大阪商人のぬけ目のなさで、織田作の名をガメツク利用しているのだが、この看板にはなんとなくコッケイ感があり、憎めない。織田作が八方やぶれの生き方をしたので、そんな名をつけたのであろうが、ドライカレーとはあまりにも非文学的な名称で、故人もさだめし地下で苦笑しているにちがいない。トラは死んで皮をのこし、織田作死んでカレーライスをのこすということか。
精華小学校の裏通りは、戦前からすし屋横丁として親しまれていたが、現在、この通りにすし屋は六軒しかない。昭和初期にはひとサラ五十銭で、"おどり"と称し生きたエビをくわせてくれた。すしをほおばると口の中でエビがぴくぴくおどるので、"おどり"というのだ。おどるアホウに見るアホウ、おなじアホウならくわねばソンソンと、三サラたいらげても一円五十銭であった。あるすし屋の店頭に、堂々とバーベキューの看板がでているのにはア然とした。一部のすし屋はすでに食堂化し、親子ドンブリまで扱うご時世だが、バーベキューには二の句がつげなかった。すしはナマモノ。江戸前(?)にぎりずしをくう横手でバーベキューをパクつかれてはどういうことになる?清元をききに行ってシャンソンが流れてきたようなものではないか。にぎりずしをくうには、にぎりずしをくうムードが必要。この営業感覚こそ、すし党の味覚神経を無視したドライ商法の最たるものだろう。
市電停留所の北側の通り筋にはアーケードがある。アーケードのなかを秋風が吹きぬける。妙見裏の酒を売る店々は、酒のうまくなる秋の季節を待っていたのだ。
ぼくは、山へクリをひろいに行った、少年の日のことを思い出した。無性に、クリがたべたくなった。千日前には、そのクリが年中ある。
楽天軒で"天津甘栗"を買って帰った。
(「浪華の夢のあとさき」より)
|
|
「盛り場には寺がある」
(昭和39年9月24日 大阪新聞「ブラリ盛り場」掲載) |
千日前には、お寺が三つある。有名な法善寺−といっても、現在本堂は再建されておらず、寺のない法善寺であるが、親はなくとも子は育ち、寺がなくても法善寺の名は全国津々浦々までトドロキわたっている。戦前には千日前の通りにむかって門があったが、焼けていまはあとかたもない。そのかわりに“天竜山法善寺”の碑がたった。
もう一つは、スバル座南隣の竹林寺だ。ここもさいきん門の左横に“浪速霊場・千日前・弘法大師”の碑をたてた。ムカシは、スバル座のある場所もこの寺の土地であったから、境内もひろびろとしていて、ハトがたむろしていた。二十一日のお大師さんの日には、どこからともなく善男善女がゾロゾロおまいりに現われて、信玄袋のなかから米をつかみ出し、ハトに投げあたえた。近ごろ、お寺まいりをするような善男善女はいったい、どこに姿を消してしまったのか。世は悪男悪女ばかりになったのであろうか。亀屋忠兵衛の墓がここにある。「カネより大事な忠兵衛さん」という梅川の表現には、あまりに大阪的でエゲツないと抵抗を感じるムキもあるらしいが、梅川はカネのために苦界に身を沈めたふしあわせな女性。こんな女がカネのありがたみを知り、一にもカネ、二にもカネ、カネのないのはクビのないのも当然やと思うのは当然のハナシで、そんな彼女が「カネより大事な・・・」と悲痛なサケビをあげるところにこの露骨な愛のコトバは、万金の重みがあるのだと思いたい。
バー、アルサロの女性に、いくらモテたといっても「カネより大事な」というほれられかたは、めったにしないものである。カネの切れ目がエンの切れ目。そう思えば水商売の女性相手の情事はいたくむなしいが、人間、カスミをくって生きてはいけず、ゼニが介在するのはどうにもいたし方のないことであろう。ネオンの光りが交錯し、明滅する雑踏千日前の一隅にアブラににじんで薄よごれた奉納ちょうちんのあかり。ゆらめくロウソクの灯。たちこめる線香のけむり。東京の浅草、京都の京極、名古屋の大須と、古い伝統のある盛り場には、みんな寺があり、それが一種の情緒になっているのだ。竹林寺の前に、かつては千日前名物(?)共同便所があったが、風のつよい日には、えもいわれぬニオイが通り筋一帯にフクイクとただよい流れ「これでは営業妨害や」と付近の飲食業者がケッ起した。軒並みぽんぽんと陳情書にハンコを取り、市会議員を動かして取りこわしてしまったが、人波あふれる千日前に一か所の共同便所もないのは不都合だと、その後、復活の声が高まったこともある。
だが、だれにしたってこんなものをじぶんの地域にもってこられては迷惑千万。“原子力潜水艦”みたいにほうぼうで敬遠されて、このハナシ、ションベンになった。寺は、もう一つ、市電停留所の前に妙見さんがある。尼寺のないのが残念である。
(「浪華の夢のあとさき」より)
|
|
「うどん・派出所」
(昭和39年9月28日 大阪新聞「ブラリ盛り場」掲載) |
かつては千日前の敷島劇場を中心に、そのあたり一帯にうどん屋が立ちならんでいた。丸福とか、丸ナントカとか、すべて屋号に丸のつく大衆うどん屋である。それがいまでは、うどん専門の店が通り筋にタッタ一軒。うどんなら大劇南横の"はつせ"という、千客万来よくはやるグランド・うどん屋にどこもタチ打ちできなくなったのだ。
タカがうどん屋などとあなどっては不覚をとる。"はつせ"の水揚げは、まことにたいしたものだそうだ。ピークのときはヘタな団体旅館も顔負けするくらいにゴッタ返し、さながら戦場のようなさわぎになる。いまでは完全にミナミの名物的存在。新築して、三階を建てまして、スキヤキもやればフグ鍋もやる。階下はうどん一式、丼物、和洋食となんでもこいの大衆マンモス食堂。持ち帰りのみやげ用に、すしの折り詰めまで売っている。うまくて安くて分量が多い、ということをモットーにして、あけすけで気取りのない千日前商法が図に当たり、こんにちの"うどん屋王国・はつせ"を築き上げたのである。
しがない屋台の夜泣きうどんもうどん屋なら、カネもうけでふくれあがった"はつせ"のごとき大うどん屋もうどん屋。千日前で財閥(?)になろうと思えば、うどんのタマかパチンコのタマか、ホステスの上玉をそろえることであろう。
大劇通りを越えて南へ歩くと、千日前もはずれだという、ゴミゴミしてうらぶれた印象が強かったが、吉本のあき地に"なんばボーリング"が完成して、スッカリ面目を一新し、町全体、夜があけたように明るくきれいになった。
以前はこのあき地に小屋がけのストリップがかかり、ドロ絵の具で描いたハダカの女のあやしげな絵看板がならんでいた。また例年正月にはテント張りの大サーカスがお目見えして、木戸で呼び込みの男が「イラハイ、イラハイ」と客を呼んだ。ヒフがたるんでカビのはえたような巨象(?)がねむたげな目をしてクサリにつながれていた。盛り場が近代化され整備されていくうらには、時代に取りのこされてさびしく追いやられてゆくものもあるのだ。
南の辻のかどに巡査派出所があったが、ボーリング場ができて、立ちのいた。いまは、巡査派出所は、大劇と千日会館のあいだに一か所あるだけだ。こぢんまりとした清潔な派出所だが、千日前にタッタ一つのささやかな"警官の城"である。大千日前の秩序は、このマッチ箱のような派出所によって保たれている。
佐渡へ佐渡へと草木もなびき、盛り場へ盛り場へと人々は蝟集(いしゅう)する。毎日、何千何万何十万という通行人が、この派出所の前を通る。そのなかには家出娘も、スリも、拐帯(かいたい)犯人も、痴漢もいる。彼らは一瞬ギョッとする。顔色をかえる者もあり、なにくわぬツラで通りすぎるものもあろうが、とにかく一応心胆を寒からしめる効果はあるのだ。無言の圧力。デモンストレーション。盛り場の派出所は、それだけでじゅうぶん存在価値があり、意義があるのだ。
(「浪華の夢のあとさき」より)
|

